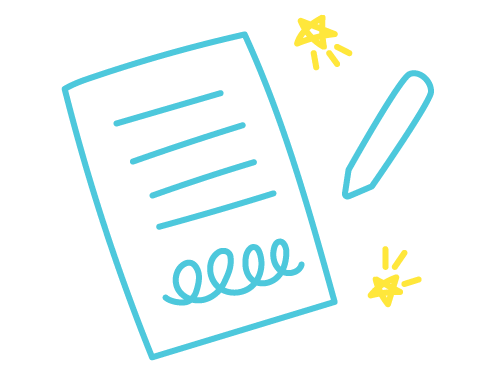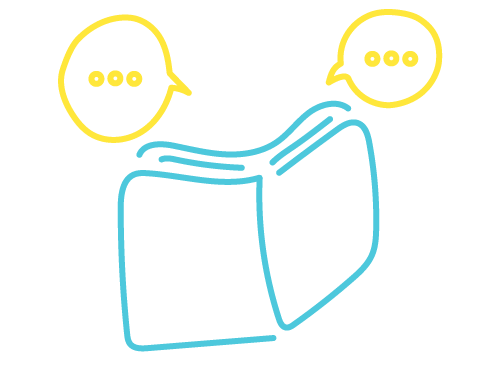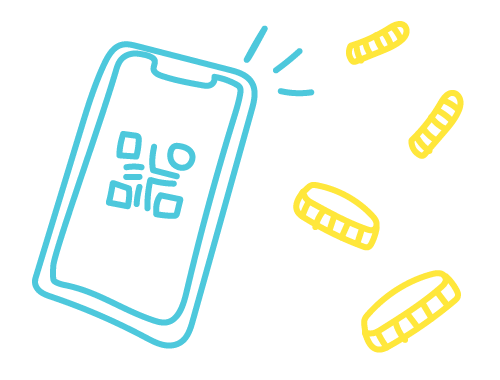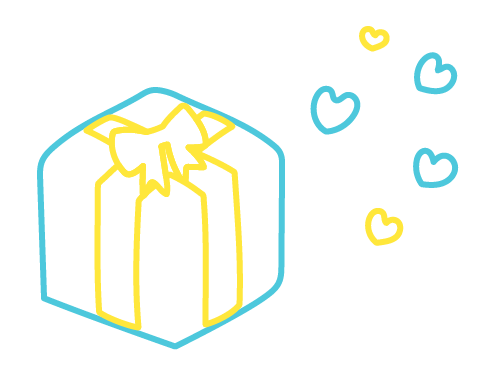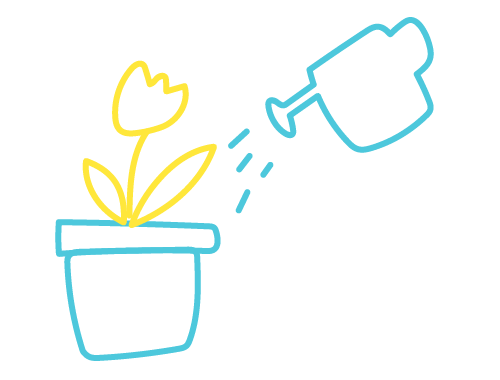- キャンペーン
-
カテゴリ
読書記録:スタンフォード式 人生デザイン講座(ハヤカワ文庫)
上記リンクではアフィリエイトを利用しています。 読んだ本をメモしておくのもいいかもしれないと思ったので、さっそく年始からスタート。思いついたらやってみてうまくいかなかったらやめるでも、全然いいのだ。やらないよりははるかにましだ。そういうことを2023年に学んだように思います。

「新自由主義」の構造転換 0ー1
「新自由主義」という言葉を、まるで「ショッカー」のように、「出たな、ショッカー!」という使い方で、私(たち)は語りすぎたのではなかろうか。 「新自由主義」の外から、「新自由主義」に対して、単にラベルを貼るのではなく、「新自由主義」の中から、「新自由主義」の論理の内部記述をしていきたいと思う。 ということを、さっき考えた。

シャネルNo5をめぐる2つの考察(ココ・シャネル関連の文献調査 3)
「文献調査1」の本の中に、シャネルNo.5という有名な香水に関する考察を行っているものが2冊あった。 テイラー・マッツエオによる『シャネルN゜5の秘密』と、大野斉子による『シャネルN゜5の謎 帝政ロシアの調香師』だ。 似たようなタイトルの本だが、前者はシャネルが主人公となって、一つの物語が紡がれている。後者は、エルネスト・ボーが主人公だ。シャネルやディミトリ(ドミトリー)・パヴロヴィッチ大公の陰に隠れて、N゜5の開発者としてクレジットされているだけだ。 しかし、マッツエオは書いている。 「しかしその香りの開発をめぐっては、数々の謎と疑問が残されている。それはシャネルN゜5の伝説のなかで、もっとも興味深く、複雑で、熱い議論の対象になってきた物語だ」p80 私自身もアルデヒドを用いた香水を作ったのは、シャネル社がはじめてだと思っていた。しかし、マッツエオの本では、それらはすでにあり、シャネル社はアルデヒドを大胆に用い、その後のキャンペーンによって、最初の伝説を作り上げた、ということが画期的だったのだ、と書かれている。 香水の香りは、ある意味で記号化されている。ファミリーというカテゴリーに分類され、その中で、いくつかの系統があり、表現はウッディやフローラルといった用語で表現される。ただ、それにもまして、誌的な表現が存在する。 マッツエオの本では、シャネルの言葉から「そう、あれこそ望んでいた香りだったわ。ほかのどれとも似ていない香水。女性の香りのする、女性のための香水だった」という部分を引用している。女性的な何か。それがマッツエオの指摘するシャネルN゜5の香りの根底だ。 ところが、大野は、ボーが祖国で見た風景を、香りの核として指摘する。ボーは、次のように語っている。 「私がシャネルN゜5を創ったのはどんな時期だったと思いますか?まさに一九二〇年のことです。私が戦争から帰還するときでした。私は北極圏にあるヨーロッパ北部の田舎に配属されていました。白夜のころ、そこでは湖や川がたいへんみずみずしい香りを放つのです。私はこの香調を記憶にとどめ、作り上げました」p266 マリリン・モンローが寝るときに数滴つけると述べたシャネルN゜5。 そうして、セクシーで官能的なイメージが、シャネルN゜5には付随した。しかし、ボーは、この香りはいわば風景が発する香りだと述べたのだ。実際どうなのだろうか? シャネルN゜5をつけたいと志願する向きは、この2冊を読むことで、踊らされない認識を手に入れることができるだろう。 「

ココ・シャネル関連の文献調査 2
1986年2月号の『marie claire』にココシャネルの特集が大々的に掲載されると、翌年5月から海野弘による「ココシャネルの星座」という連載が、1988年5月号まで掲載された。それが、1989年に中央公論社から『ココ・シャネルの星座』として書籍化されている。おおよそ、日本において、人間シャネルが日本人の手によって具現化されたのは、この書籍を皮切りにしてだろう。 ただ、海野弘は、あくまで1920年代のシャネル最盛期の記述で、全体像ではない。その後、日本人による伝記の試みがあるにはあるが、翻訳の内容を超えるものとは言い難い。1990年の秦早穂子の本は、そもそもポール・モランのシャネル本の訳者であるので、その訳業+αとして、冒頭にシャネルが提案したルックの写真が多めに掲載されているのがうれしい。 日本人独自のシャネル伝記としては2002年の山口昌子による『ココ・シャネルの真実』が良い。というのも、産経新聞のフランス特派員であった山口は、フランス事情通であり(文庫版あとがきの鹿島茂もそう書いている)、書きにくい部分についてもキッチリ筆が載っているのがいい。戦後の、有名人たちとの交流についても、マンデス=フランスとの会合を望んで引き合わされたシャネルが、ドゴールについて長い時間話したというエピソードとか、ちょっと面白いことも満載だからだ。要するに、シャネルを英雄然と描いていないがゆえに、『ココ・シャネルの真実』は今でも読む価値が十分になるといえる。 藤本ひとみの『シャネル』は評伝ではなく、小説形式なので、普通に読みやすい。史料の提示があって、記述を進めていくという形式がわずらわしい人は、この小説から読むといいかもしれない。また山田登世子の『シャネル 最強ブランドの秘密』は、タイトルからするとブランド論ぽいが、2021年にちくま文庫化された『シャネル その言葉と仕事の秘密』の方が内容をキチンと表現しているように思われる。評伝的なものが好きなら、こちらを先に読むといいだろう。 2012のハル・ヴォーンの『誰も知らなかったココ・シャネル』は先に書いたように戦中戦後のシャネルの姿が史料とともに記されていて大変に面白い。この本が出て以降は、シャネルをそんなに英雄然として描けなくなったろう、と思ったのだが、割と恋も仕事もつかんだ女的な規範化がみられる。面白いことだ。 ハル・ヴォーンの内容を踏まえたうえで面白い翻訳書としては、『シャネル、革命の秘密』がいい。伝記作家はあまり服や服飾産業について詳しくないので、そちらの方に筆を伸ばさないが、このリサ・チェイニーの本では、そうしたデザイナーとしての動きも書かれている。デザイナーとして意義だけではなく、史料を使って、戦後のデザイナー・ココ・シャネルについて書こうとしているのが共感できる。 2016のイザベル・フィメイエの『素顔のシャネル』は、秘蔵写真が多くて面白い。大きいサイズの本なので、場所をとるのが難点。ただ、秘蔵写真の中で、シャネルに写真の顔もみたくない相手のところは切り落としてしまう、というふるまいに及ばれたいくつかの写真を見て、ワクワクしてしまった。ここには誰がいたんだろう、なんていう、そういう想像を掻き立てる秘蔵写真がたくさんのっているので、今までの文献を通読して、シャネルをもっと知りたい!と強く願う人なら、読んでみてもいいのかもしれない。 いずれにしても、シャネルはオードリー・ヘプバーンと同様に、なんでか人気があるなあ、と感じた。

『誰も知らなかったココ・シャネル』(文藝春秋)
ハル・ヴォーンによる『誰も知らなかったココ・シャネル』は、今回シャネルのことを学ぶ途中で、手に取った一冊ですが、大変に面白いです。 原題が「Sleepnig with the enemy coco chanel's secret war」ということで、なんとも刺激的です。 要するに、シャネルは戦時中、ドイツ人諜報と恋に落ち、その諜報はシャネルをスパイとして使っていた、という事実に関する本ではありますが、シャネルはその加担を理解していたのか否か、積極的だったのか否か、という部分が興味深いです。 他の伝記では、その部分に関して、消極的で仕方がなかったがゆえに協力、という印象で書かれるか、沈黙するかではありますが、この本では明らかに自覚的で積極的な印象を受けます。 帯には「ナチスのスパイだった!」と煽りがありますが、内容をよく読むと非公式的外交官のような役割と理解できます。 ココ・シャネル個人やシャネルというブランドに興味のない向きにも、第二次世界大戦の占領下フランスを知る物語として、面白いと思います。