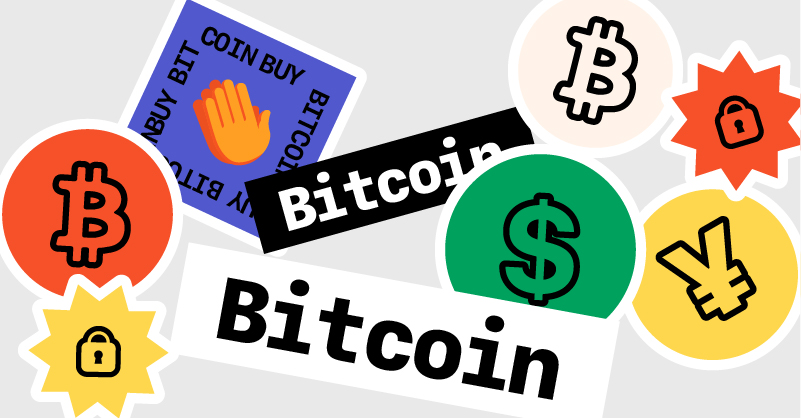コロナな毎日の中で、「死」を考える
新型コロナウィルスが猛威を振るっています。
日本ではなぜかコロナウィルスによる死者数が少ないですが、諸外国では多くの人々が命を落としています。日本においても著名なお笑い芸人が亡くなり、また連日のニュースで死亡○○人と伝えられ、人々は怯えているようにも見えます。
しかし、日本人は、「死」というものを本当に認識し、身近に感じているのでしょうか。
貧困のない消費社会、医療の発達により、現代は歴史上例のない「人が死なない」時代に入っています。そのこと自体は結構なことなのですが、とくに戦後、人々は意識的に「死」を遠ざけているように思えます。それは、近年の葬儀の在り方の変容にも表れています。
これまでの長い歴史の中において、死は常に身近にあるものでした。冒頭の画像は、平安~鎌倉時代に描かれた『餓鬼草子』です。これは、飢えに苦しむ餓鬼道の様子を示すものですが、描かれる死者の傍らには供物が供えられている。これから当時の葬送の在り方が読み取れます。すなわち、当時の庶民の間では、火葬でも土葬でもなく、そこらへんの道端や岩陰などに置いておくだけの「風葬」が行われてたということです。火葬も古くから行われてはいましたが、現代のように主流になるのは戦後からであり、それまでは風葬や土葬も一般的な葬送方法でした。
また、養老孟司著『死の壁』は、古人にとって死は非常に身近なものだったことの例として、中世に描かれた『九相詩絵巻』をあげます。『九相詩絵巻』は、死体が少しづつ腐っていく様子が極めてリアルに描かれており、自然科学がない時代にここまで描けることを証拠に、死が身近にあったことを述べています。
一方、近・現代の葬送の在り方はどうでしょうか。
近年の日本における火葬率は、1896年(明治29年)が約27%、1955年(昭和30年)が約54%、1984年が約94%という研究結果(『民俗小事典 死と葬送』)が示すように、戦後から火葬が主流となってきています。それ以前は、庶民の間では土葬が一般的であったようです。
さらに1960年代から70年代にかけての高度経済成長を境とし、大きな変化が起こっています。家での死から病院での死へ、地縁的関係者による葬儀から葬儀業者による葬儀へ、家ごとの墓地から大規模集合墓地へ、などの変化です。
特に葬儀の主体が血縁的・地縁的関係者から、葬儀社へと移り変わったことは重要な変化だと思います。伝統的な葬送では、家族などの血縁的関係者が湯灌(入棺する前に死者の身体を湯で洗うこと)や入棺を行っていました。また、自宅で葬儀を行うので、地域の人々が葬儀の会場、装具作りなどを手伝っていたのです。それらがすべて葬儀社の手に移りました。
これに伴い、野辺送り(葬列をつくり、死者を墓地や火葬場へ運ぶこと)をはじめ、多くの儀礼が省略・簡略化されました。葬儀場や火葬場などは、今ではどこも清潔で、こざっぱりとしていて、一見するとどこにも「死」のイメージが湧かないのは私だけでしょうか。
また、近年では家族葬という言葉も目立ってきています。核家族化が完了した昨今、親戚や地域の人々は葬儀には呼ばないということなのでしょう。旧来の友人知人たちは、葬儀に参加しない代わりに、自分たちだけで偲ぶ会を行うということも聞きます。現代の人々は「死者」や「死体」をみることが極端に少なくなっているということです。
都市化・近代化の過程で、明らかに人々は死を遠ざけるようになってきています。
死穢忌避の観念や死霊畏怖の観念は希薄してきているとも言えそうですが、やはり死に接する機会は少なく、意識的に死を遠ざけているのだと思います。
ただ、これは都市化されていくにあたり、自然の流れでもあると思います。
しかし、人は必ず死ぬのです。この事実が変わることはありません。
そうであるのであれば、死を遠ざけ、蓋をし、極力関わらないようにすることは、賢い選択と言えるのでしょうか。
「人は死ぬ」という真理を、感ずることなしには、今を生きることに綻びが出てくるのではないのかと思うのです。
参考文献
『民俗小事典 死と葬送』新谷尚紀、関沢まゆみ
『死の壁』養老孟司
『葬式仏教の誕生』松尾剛次









![[完全自分メモ]Clubhouseで残念なRoomに遭遇した反動で一念発起しかかった話w](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/spotlight-s3-001/article/kzjpd5kcv_20210817_112426_1629167064579Image 005.png)